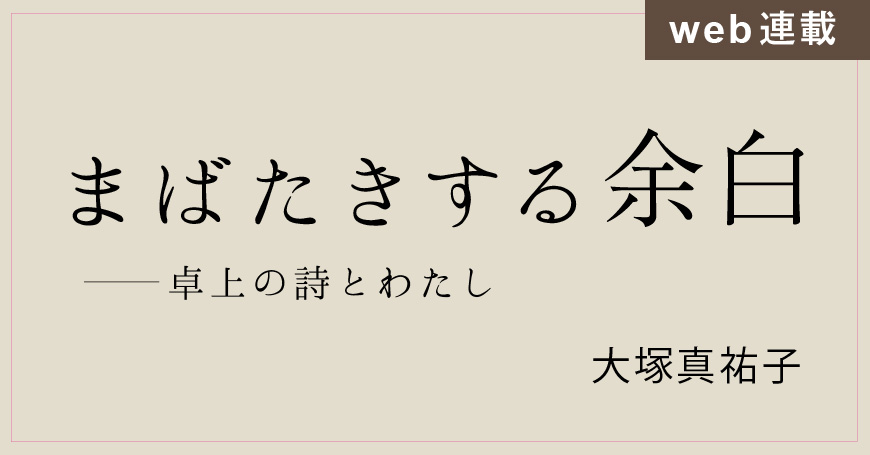
闇
吉田加南子
わたしが
わたしより先にある
ということ
闇
わたしが
わたしよりも深く沈むとき
闇
何も通らなかったかもしれないのです
でも
わたし
あとなのです
何も通らなかったということの
闇
わたしのなかって
光が通りすぎてゆくときにしか
ないのかもしれない
闇
いっしょ
でも
わたしといっしょにいるものが見えないのです
闇
何かとならびあうことはできません
抱きあうことができるだけ
闇
はばたくとき
沈むのです
闇
ほどけません
むすばれていないのに
わたしを見ていないもの
まなざしによってしか
闇
わたしがほどかれてゆくときにしか生まれない
光
闇
でも
わたしは光が生まれる前からいるのです
闇
わたしを見ていないあなたが
でも
わたしをうしろから抱きとめているのです
*
闇が裂ける
裂けた底であなたと会いたい
闇
わたしが
もし光をつかんだら?
血はわたしの手につくのです
闇
光を抱くこと
それがわたしの踊りです
闇
みちです
じぶんがじぶんをさかのぼるための
闇
匂いにならなければいけないのです
闇
ゆきどまり?
いいえ
はじまりです
*
ゆく
って
へりをこえること?
闇の
闇
中心を
じぶんのそとに持つということ
闇
わたしの濃さがほどけてゆくときに
でも
浮かんだまま残っている
わたし
闇の白さ
むこう
本質
傷
*
闇をまわすと
光です
(一九九三年/『定本 闇 見ること闇が光となるまで』(思潮社)より「Ⅳ」)
編注:引用中の斜体部分は原典に傍点が付いている箇所です。
当時の交際相手が働く本屋の同僚に彼がいた。本を買いに行くと彼が会計をすることがあったが、言葉を交わしたことはほぼない。
彼は音楽にくわしくバンドを組んでいた。彼の作る曲は、懐かしい旋律と軽やかな詞が既存のバンドを連想させたが、好きな類の楽曲だった。彼の演奏を聴くため、渋谷のライブハウスまで足をはこんだ。何組か演奏するうちのひとつが彼のバンドだった。
どちらかといえば闇の割合の高い空間なのにその質感は明るく、この明るさをともにする人たちの輪郭が、その日はまるで一筆書きのように連なって見えた。明るい闇がそのときどきの音や声で自在にふるえるとき、自分の身体もこの一筆書きのひと筋だと強烈に理解することが、自分にとって音楽を聴くということなのだと知った。このとき感じた音楽についての感覚を、わたしはその後も長らく持ちつづけたが、彼の演奏を聴いたのはその一度きりだ。交際相手とはとうに別れ、バンド名も彼の名前さえ思い出せないのに、彼からもらったJONI MITCHELLのCDはいまも手もとにある。これをあなたが聴いていたら素敵だと思う、という言伝てとともに受けとったそのアルバムを聴くとき、彼の言う素敵とは何かをいまも考える。
踊り手の彼女とはまた別の交際相手の紹介で知り合い、ふたりで会うようになった。
彼女と自分には似たところが全くないようにみえた。彼女は広い視野でつねに自身の立ち位置を把握し、自分の考えを明確に歌うように話した。表情や身のこなしも、彼女のいるそこが舞台であるかのようにいつも華やかで、彼女の前に立つと、自分も何らかの役割をもつ有能な演者になれたような気がした。彼女と自分の隔たりのうちに、自分がこれからどう生きていきたいのかを、見定められるような気もしていた。
『闇』という詩集を彼女におくったのは、現象でも感覚でもあり、単一でも複数のようでもある〈闇〉という存在へ、〈わたし〉をひとつずつ呼応させ、はためかせるその表現の数々に、彼女のあり方と重なる部分を感じたからだが、詩集をおくるなど恋人にもしたことがないのに、よくできたものだと思う。
彼女がわたしと会うことをどう思っているのか、わたしにはわからなかった。彼女と自分が会うことの意味を、濃密なその詩集の言葉に託そうとした、自分の陳腐な自尊心による行為だということがいまならわかる。
彼らとわたしのことを知る人は、もうだれも近くにいないのに、JONI MITCHELLの歌と吉田加南子の詩はかわらず目の前にあり、目にするたびわたしが彼らを思い出すことをだれも知らない。知らないことが無と同義なら、無をなぞる指として言葉を用いることが、わたしにとっての詩なのだと思う。
大塚真祐子
文筆家・元書店員。
2022年より毎日新聞文芸時評欄担当、朝日出版社WEBマガジン「あさひてらす」にて「何を読んでも何かを思い出す」連載中。
執筆のご依頼はこちら→komayukobooks@gmail.com
目次
