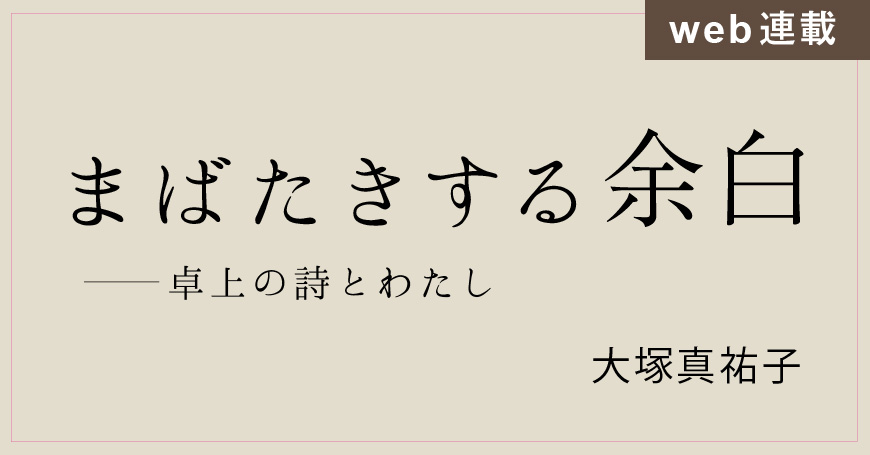
紙風船
黒田三郎
落ちてきたら
今度は
もっと高く
もっともっと高く
何度でも
打ち上げよう
美しい
願いごとのように
(一九六四年/『もっと高く』(思潮社)収録)
顔のなかのひとつ
黒田三郎
始発の通勤電車を待ってフォームに行列をつくっているひとびと
その行列のなかにまぎれこんで
僕はほっとひと息つく
行列のなかにまぎれこんでしまえば
僕も普通の通勤者のひとり
僕が遅れて勤めにゆくことに気のつく者は誰もいない
たった今小さなユリを幼稚園へ送って来たと知る者は誰もいない
顔であることになれきった顔の群れに入り
僕もまたその顔のひとつになる
始発の列車がゆれながら
しずかにフォームにはいって来る
瞬時
行列はくずれる
我れ勝ちになだれ込む
そのとき
くずれる顔
顔であることになれきった顔がくずれる
それも
ほんの一寸のことだ
座席に坐ってひとびとはとりかえす
顔であることになれきった顔
よそゆきの顔を
坐りおくれて
僕は戸口に立ち
しずかに外を見る
見なれた光景
飲屋の隣は洋品店
その隣は貸本屋だ
何もかも昨日のまんまだ
外を見ることで
僕もよそゆきの顔をとりかえす
(一九六〇年/『小さなユリと』(昭森社)収録)
夕焼け
黒田三郎
いてはならないところにいるような
こころのやましさ
それは
いつ
どうして
僕のなかに宿ったのか
色あせた夕焼け雲のように
大都会の夕暮の電車の窓ごしに
僕はただ黙して見る
夕焼けた空
昏れ残る梢
灰色の建物の起伏
影
美しい影
醜いものの美しい影
(同上)
詩というものにはじめて触れたのは、八歳の冬のことだ。小学二年生の国語の授業で、担任の先生から詩を書いてみようと言われ、まっさらな原稿用紙が配られた。
記録的な豪雪の年で、そのころ暮らしていた東京郊外の町にも、長靴がしずむほどの雪がたびたび積もった。放課後、級友の家のそばにある保安林で、集まった友人と雪のすべり台を作った。坂の片側に凹みをつくって階段状にし、のぼれるよう工夫をした。小さな坂道にすぎないが、そのときはすごい力作ができたと思っていた。帰る間際に立ち寄った級友の家のほの暗さと、足裏に触れる短い毛足の絨毯を、他人の家の違和感とともにおぼえている。その日に見た、保安林に降る雪のことを詩にしたのだった。雪が降ると、林が一面に白く明るく見えること、枝や幹のかたちが、雪にふちどられて浮きあがって見えることなどを、拙く幼い主観で書いたはずだが、書いた詩句はまったくおぼえていない。
進級とともに市内の別の小学校への転校が決まっており、当時の自分はそれをつよく拒絶していた。両親が建てた一軒家は、通っていた小学校の学区外だったがわずかな距離なので、いまの学校のまま通うことはできるはずだと主張した。しかし子どもの言い分がとおるはずもなく、しまいには食卓の下に籠城するしか抵抗の策がなくなった。食卓の上に広げられた新居の青焼き図面と、娘の喜ぶ顔を想定していただろう父の、戸惑った様子が記憶にのこっている。
それらの印象的な出来事があいまって、国語の授業ではじめて書いた詩のことを、思いのほか鮮やかにおぼえている。そしてその数年後、同じように国語の授業で黒田三郎の「紙風船」を目にしたとき、言葉で表現するというあらゆる情動や行為において、この詩はもっとも完璧な直喩のかたちをしている、と思った。それくらいの衝撃をうけた。こんなことが言葉や詩にできるのだと知った。しかしそのときはそれだけで、黒田三郎のほかの詩を読もうとは、長らくしてこなかった。
黒田三郎の詩は〈詩についてだけでなく、生活について考えることになる〉詩だと吉野弘が語り、〈日常的な、あるいは生活的なものを通して世界をみようとする感性〉が媒介となっていると北川透が語る。二〇一五年に夏葉社より完全復刻された詩集、『小さなユリと』に収められた、幼い娘との暮らしを描いた詩の数々は、その最たるものと考えられるだろう。けれどもなぜかその向こう側には矛盾が、複雑な倒錯のようなものが垣間見える気がするのだ。それは、「生活」を書くことで自らを日常にむすびつけようとする、詩人自身の懸命な指先であり、日常との隔たりを不意にあらわにされた、詩人自身の孤独な背中にも見える。いったいそれは詩人のなにに由来するのか。それもまた詩人の言葉にいつしかかき消され、背中は夜半の酩酊にまぎれていく。
大塚真祐子
書店勤務。2022年4月より、毎日新聞文芸時評欄にて書評を担当。朝日出版社WEBマガジン「あさひてらす」にて、エッセイ「何を読んでも何かを思い出す」連載中。絲山秋子著『夢も見ずに眠った。』(河出文庫)解説を担当。
目次
