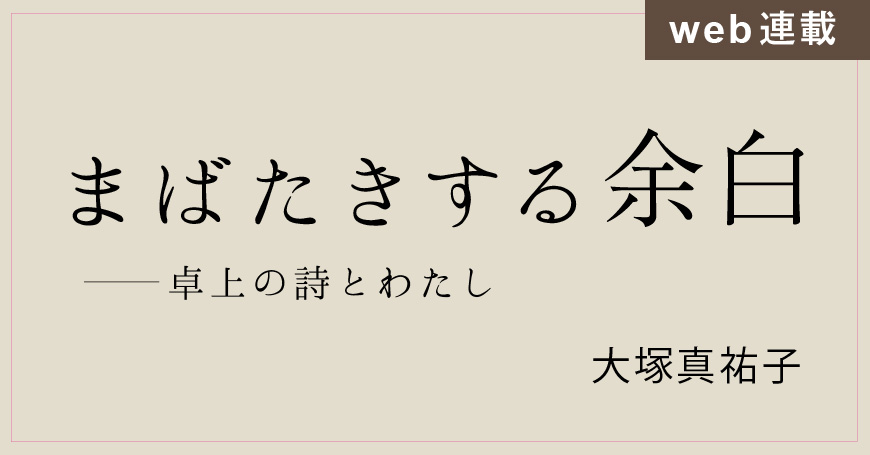
Nu
田村隆一
窓のない部屋があるように
心の世界には部屋のない窓がある
蜜蜂の翅音
引き裂かれる物と心の皮膚
ある夏の日の雨の光り
そして死せる物のなかに
あなたは黙って立ちどまる
まだはっきりと物が生れないまえに
行方不明になったあなたの心が
窓のなかで叫んだとしても
ぼくの耳は彼女の声を聴かない
ぼくの眼は彼女の声を聴く
(一九五六年/『四千の日と夜』(東京創元社)所収)
台所に立つと、掃き出しのガラス窓のむこう、向かいの棟に住む子どもの同級生が、一輪車の練習をしているのが見える。
○○ちゃんがいるよ、と子どもに声をかけると、ものすごい速さでベランダへ飛び出し、それでも呼びかけることはせず、ベランダの手摺りを使ってこれみよがしに屈伸運動をしながら、友人が気づいてくれるのを待っている。友人がこちらを見ると、本来は入ってはいけないとされる芝生へベランダから降りて、彼女のもとへと駆けていく。やりとりは聞こえない。子どもは一輪車をやってみようとはせず、彼女もやらせようとはしない。たまにベランダへ戻ってきて、生協の野菜ジュースが飲みたい、と二人分のパックジュースを抱えていくが、あとは日が落ちるまで何かしらしている。別々のことをしたり、同じことをしたり、見えたり、見えなくなったりする。
合板の開き戸にはニューヨークの夜景が大きくプリントされていた。
前の利用客のものと思われる煙草の匂いを逃すために戸を開けると、網入りガラスの窓があらわれ、ひらけば隣のビルのモルタル壁が目の前に見える。匂いが薄れると、閉めた窓にニューヨークがまたあらわれる。
夜のニューヨークには、二〇〇一年のアメリカ同時多発テロ事件によって崩壊したツインタワーが、いまもそびえ立っている。ノースタワーの頂部に立つアンテナが空を刺すように伸び、数多の窓の光が難解なパズルのようにひしめく。
九・一一と呼ばれる日にこの古いホテルで、窓にプリントされたツインタワーを見ていたかもしれない誰かを想像する。いまより明るい色味をしたジャガード織りのベッドで、湿った空気にまみれた誰か。いずれこの部屋へ行きついて、色褪せた異国の夜景を見ても何も感じないかもしれない誰か。それぞれのまなざしの明度を思いえがく。
戦後を代表する詩人と呼ばれ、そのたたずまいも言動も、鋭利な刃物ですっぱりと切り裂いたような詩句もあまりに華やかで、華やかさゆえに敬遠していたところがあった。
〈窓のない部屋/部屋のない窓〉〈耳は―聴かない/眼は―聴く〉のような対句やリフレイン、細胞の一単位まで対象に分け入ろうとするような眼や、それらを余すことなく伝えようとする精緻な言葉をあらためて見わたすと、言葉のむこうに広がる茫漠とした土地が、ふいにあらわれた。
それは言葉が意味になる前のほんの少しのすき間のような場所、人びとの感情に名前がつく前の、渾沌とした正午であり垂直の夜であって、詩人はそれらを詩という連なりによって、かたどろうとしていたのだとはじめて気がついた。詩人がかたどった新しい立体に手を伸ばすと、手はやがて影となり、影はそのまま暗い窓になった。
大塚真祐子
書店勤務。2022年4月より、毎日新聞文芸時評欄にて書評を担当。朝日出版社WEBマガジン「あさひてらす」にて、エッセイ「何を読んでも何かを思い出す」連載中。
目次
