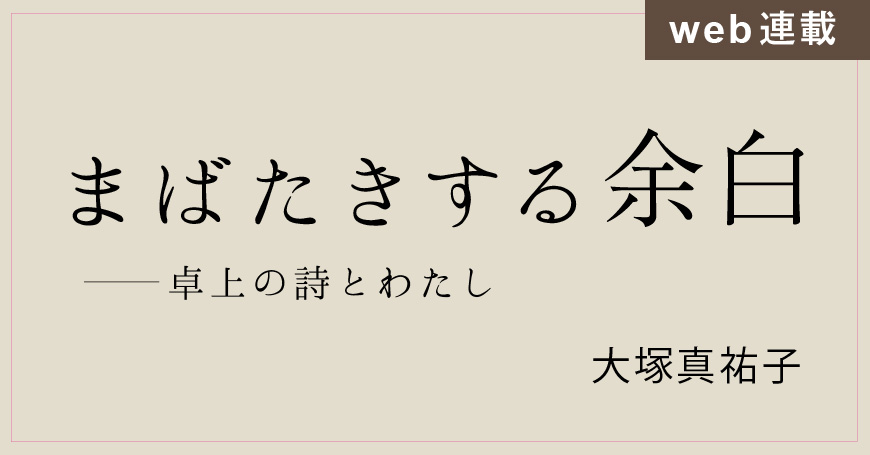
a shabby new year
北村太郎
古い窓の桟のむこうは
落日のさす竹やぶ
うす暗い湯殿にいて
湯舟に
髪の毛がいっぽん浮かんでいるのに気づいた
それはしばらくして
ゆっくり沈んでいった
わたくしは大きく目をみひらいた
それは水の中を
ほとんど横のままに
じつに長い時間をかけて下りてゆき
ついに
青い底に着いて動かなくなった
わりなき思いの
一日が過ぎて
また新しいあしたへ
恐ろしい日々へ
冬の底へ
(一九七九年/『ピアノ線の夢』(青土社)収録)
3階建のドトールの、2階が分煙フロアだった。職場の近くに新しいドトールができるまでは、毎日かよっていた。空気の濃度で混雑をはかりながら階段をあがると、テーブルはたいてい乱れていた。その前の職場ではガード下の、分煙されていないドトールにかよっていた。列車が通過するたび、天井から心音が降ってくるようだった。
日々訪れていると、きまった時間に現れるきまった人びとに遭遇した。マンツーマンで日本語を教わるアジア系の青年や、色ちがいの服を着た二人組の初老女性などがいた。窓際のカウンター席で、立ちつくす男性もよく見かけた。椅子は空いている。待ち人が出現するわけでもなく、ソーサーからカップを持ちあげ、一人ただいつも立っていた。
ときにはシステム手帳を忙しそうに繰り、ときには車の行き交う大通りを、窓から長いこと見おろしていた。来るのも出ていくのも見たことがない。気がつくとそこにいた。わたしはそこで、ねじめ正一の『荒地の恋』を、何日かかけてはじめから終わりまで読んだ。なかほどに、田村隆一の妻である「明子」と暮らしはじめた北村太郎が、元旦に届いた週刊新聞に掲載された自分の詩、「a shabby new year」を声に出して読むという場面がある。
〈古い窓の桟のむこうは/落日のさす竹やぶ/うす暗い湯殿にいて/湯舟に/髪の毛がいっぽん浮かんでいるのに気づいた/それはしばらくして/ゆっくり沈んでいった〉
シャツに浮きあがる男性の、湾曲した細い背骨を見ながら、あの人も髪の毛を見ているのだろうか、とふと思った。窓の下を走る道路の喧騒へ、ゆっくりと落ちていく一本の髪。
そのころ、結婚するつもりで恋人と部屋を借り、転居をすませたばかりだった。『荒地の恋』を少しずつ読みすすめながら、ドトールの2階にひしめく長方形のテーブルが、トランプのカードのようにひとつ、またひとつとめくられる幻を見た。めくられたテーブルは一枚の闇になった。闇の羅列のただなかで、わたしは目をみひらく「わたくし」でもあり、落ちていく「髪の毛」でもあった。見あげると水面の向こうで詩人と目があった。
細胞という細胞に満ちようとする圧力にさからうことなく、底に向かってゆらり、ゆらりと下りていくわたしは、もはや生きていようと死んでいようとどちらでもかまわない。ただ誰かを愛し、誰かに愛されたことを忘れないあるいは忘れさせないために、わたしはわたしをいっそう剥きだしにして、溶けあわなければならない。でもいったい何と?
わたしはほどなくして婚約を破棄し、部屋を出てしまった。ベランダから呼ばれた自分の名とその声を、忘れたことはない。忘れないことが何かになるとも思わない。ただわたしがいくらわたしを剥きだしにしても、いまもって日々は無表情で過ぎる。
大塚真祐子
書店勤務。『本の雑誌』の「新刊めったくたガイド」欄、日本文学の紹介を2020年12月まで2年半担当。また。朝日出版社webマガジン「あさひてらす」にて、エッセイ「何を読んでも何かを思い出す」連載中。
目次
