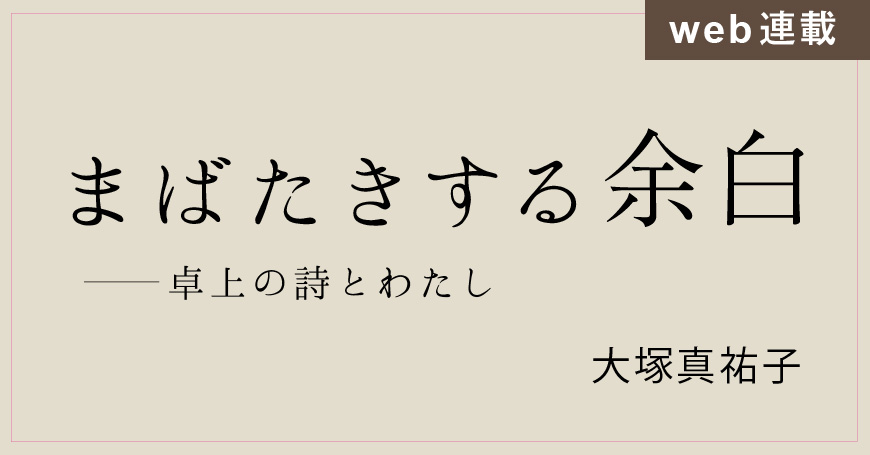
新年前夜のための詩
中桐雅夫
最後の夜
最初の日に向う暗い時間
しずかに降る雪とともに
とおくの獣たちとともに在る夜
さだかならぬもの
冷たくまたあわれなすべてのもののなかに
形づくられてゆくこの夜
ちいさな不幸が窓ガラスをたたき
人間の眼は灰の悲しみに光る
最後の歌は地をおおい
闇のなかに
聖なる瞬間はしだいに近づいてくる
死と生とが重なりあうその瞬間
「時」のなかのそのちいさな点が
われわれに襲いかかってくるまえに
なにかなすべきことがわれわれに残されているだろうか
おお その聖なる瞬間
われわれはただ知らされるのだ
すべての偉大な言葉はすでに言いつくされ
生の約束も死の約束の変形にすぎないことを
おお その聖なる瞬間
あすに向って開かれたドアからは
すべての未来が流れこみ
室内は水晶と闇の光に輝く
おお その聖なる瞬間
わたしは忘れ わたしは忘れ去られる
死骸が墓のなかに落ちこんでゆくように
わたしはわたし自身のなかに落ちてゆく
わたしの細く深い海峡のなかに
わたしの暗いあすのなかに
(一九五一年/『荒地詩集1951』(早川書房)所収)
えっ一緒に来るの、と娘が二度も言うので、そんなに言うなら行かない、と思いがけず喧嘩ごしのやりとりになった。繁忙期の激務により、翌日の旅先で昼間から寝入ってしまった母への、あれは優しさか糾弾だったのか。娘は軽やかな足どりで待ち合わせた親族のもとへ向かい、わたしは三宮の駅前でとつぜん一人になった。義父方の墓参のために訪れるのは二度目だが、関東育ちの自分にはつゆほども馴染みのない街である。
宿泊所の位置を脳内の座標で確認しつつ、繁華街を歩く。交差点に面したパチンコ店のモニターが、紅白歌合戦を流しはじめた。現状のまま書店で働くのは、もう限界かもしれない。人に割かれるべき経費は大幅に削られ、必要最小限の業務さえ手をつけられず、今日できなかった仕事は、すべて明日の自分にのしかかる。こんなことははじめに就職した書店が倒産した二十年前に、すでに経験していることなのに、この業界はなにも変わらない…そんな絶望を秋口から感じつつ働いていたら、ほとほと疲れていた。それでも街中で本屋の看板を見つけると、つい体を向けてしまう。純粋な読者の目で書棚を見ることはできないけれど、今日はなるべくただの客に徹したいと店内へ入った。売るためでも紹介するためでもなく、ページをめくって少しでも惹かれたら、その本を買いもとめようと思った。未読だったフランスの作家の文庫を手にレジへと向かう。会計してくれた男性の名札には大きく「店長」と記されていた。
中桐雅夫が神戸で育ったことは、帰京してから思い出した。妻の中桐文子による手記『美酒すこし』(筑摩書房)には、三宮の駅前で中桐雅夫の家出の場面に遭遇する記述がある。手記の横に差した、背表紙の変色した38番の現代詩文庫に、新年前夜を題名にした詩がふたつもあるのを見つけると、あの夜、大晦日の三宮をつかの間さまよった自分に回路がひらいたような気がした。
中桐雅夫の詩にはつねに揺れ動く二つの世界がある。揺れつづけるために詩が必要とされ、詩から少し遅れて言葉が、声が聞こえてくる。何かがずれている、どの詩を読んでもそのイメージから逃れることはできず、それこそが詩人の心象なのか、詩作品の鑑賞だけでは判断できないようなところがあるけれど、前述した妻の手記を読むと、彼女の冷徹なまなざしの向こうに、赤く滲んだ詩人の傷口が、生々しく浮かびあがる。詩人の魂はおそらく、人が生きていつか死ぬということの悲嘆のうえに存在する。詩人はそれを自分の身体ごと、全うしようとしたのかもしれない。
あの日購入した文庫には、恋愛をめぐる作家自身の告白が綴られていた。わたしはそれを娘からの連絡がくるまで、自分のことのように読んだ。三宮のドトールで、わたしを知る人の誰もいない街で、大晦日の夜に。
大塚真祐子
書店勤務。2022年4月より、毎日新聞文芸時評欄にて書評を担当。朝日出版社WEBマガジン「あさひてらす」にて、エッセイ「何を読んでも何かを思い出す」連載中。絲山秋子著『夢も見ずに眠った。』(河出文庫)解説を担当。
目次
