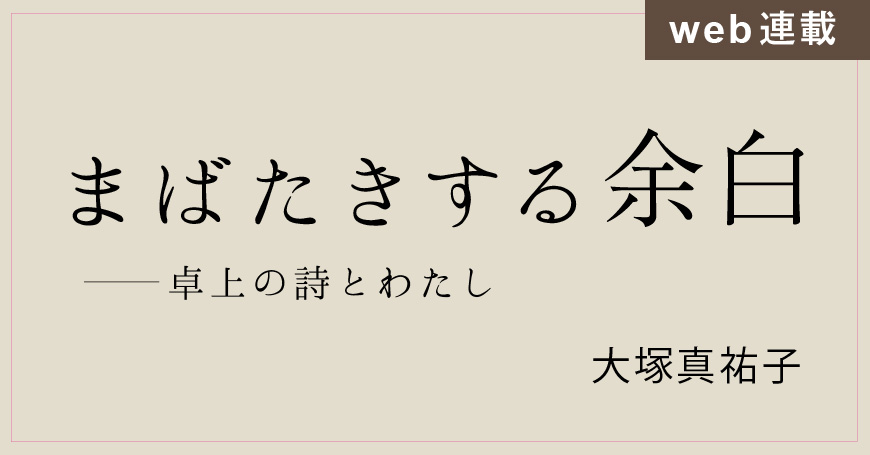
ひとりぼっちの泳ぎ手
衣更着信
苦い潮をかんで
泳ぎ手は波の谷間へ落ちる
震えながら
軽わざ師のようにとぶ
かれが欲しいのは
呼吸するためのわずかばかりの空気
まつげから涙に似たものをこぼし
からだがぬれた袋のように水から現われる
それはよろこびをつめて流れた
それは悩みをつめて漂った
今は血と水と汚れを包んで
あるいはとげとげしい恐れと逃げ去りたい心を隠して
ひとりぼっちでおびただしい波を乗り越える
黒い髪が海にはよく似合う
(一九七六年/『庚申その他の詩』(書肆季節社)収録)
孤独な泳ぎ手
衣更着信
いわしの集団のなかで泳いだことがあります
夏の真さかりの、まだ五センチくらいの小いわしの群れが
浜辺まで近寄って来ることがあるでしょう
近寄っては離れ、固まっては小さく散る
その辺は、小さな雲の影みたいに濃紺色が走るんです
うす緑の、勢いを誇っている海の水に――
いたずら心を起こして、魚の群れのほうへ泳いでみました
かれらがせいいっぱい陸に近づいたときに
なにしろ、そんな時刻(ちょうど十二時、わたしは昼食前)に
この浜で泳いでいるのは、わたしだけでしたから
人家を出ればすぐ浜辺ですが、危険だとか
水が汚れているとかいって、子どもたちを泳がせないんですよ
親じゃない、学校の先生が(秋になるとちゃんと
いわしをとってもうける商売はあります、余談ですが)
泳いで近寄っても、魚は逃げませんでした
意外にも左右にさっと開いて、わたしを群れに
はいらせてくれた、そしてそのあとを閉じるんです
つまりわたしは小いわしの集団の真ん中にいる
これはどういうことだろう、人間の害意をかれらは想定しないのか
ねこが人に親しむのは、人間の動作がのろいので
同類に対するような警戒心をもたぬのだそうですね
いわしどもは、わたしが大魚でないと知っているのか
逃げないとあれば、いわしのなかを泳げないものか
手が魚をかきのけたりなでたりできそうだ
二の腕あたりをくぐったり、腹のしたで盛り上がったりするだろう、魚は――
しかし、さすがです、魚は絶対に人間にさわらせませんよ
わたしの泳ぐスペースを最少限に許しているのに
手を動かすだけは、そのたびに離れるのです
これが魚の技術でしょう、あたりまえのことだが感心してしまう
いくらこちらがスピードをあげてみても、方向を急に
変えてみても、与えられるスペースは最小限です
雲からとはいわぬまでも、燈台のうえから見おろしたら
緑の水に紺の魚群、そのなかで手足を思いきり広げて
泳いでいる黄いろいパンツの人間は楽しい絵ではないか
しかし、わたしが思い浮かべていたのはlifeということばでした
泳いでいると妙なことを考える
その真ん中にいるのにさわれないんですよ、lifeは――
至近距離にあるのに、道を開いて迎え入れ
ときにむこうから近づいて来るのに、さわれないんです、lifeは――
太陽が激しく輝いていても
潮風がさわやかに吹いていても、これだけ沖へ出て来ても、
沈下海岸に積まれたテトラポッドがかすんで見えるほどになっても
すぐそばを泳ぐ魚に手が届かないように
これだけ歳月を過ごして来ても
目がくらむほど暮しを続けて来ても
わたしはもどかしい、わたしはさわれなかった
あれがlifeなんだ、今こそ悟る
あれがlifeなんだ
(一九八三年/『孤独な泳ぎ手』(書肆季節社)収録)
Sous La Mer
この題は野間佳子の絵から
衣更着信
疲れた泳ぎ手
疲れ果てた泳ぎ手の心は、真っ黒い思いだけでもない
希望的な気持ちが距離を引き寄せる
だから泳ぎ切ったと立ててみる足は何度も
底の砂につかない、またその次ぎも
旅路
浮かなくなった水死人
底に着いた水死人
水中を渡る音は
泡の頂きの波の山の
したを通って旅をする
もぐらのめくらの四分五裂の
旅を手さぐりで
出会うのは目や鼻に
痛い塩の味
なめられる舌つつかれる耳
藻を引き寄せて
横たわる
(一九八三年/『孤独な泳ぎ手』(書肆季節社)収録)
玄関の外側のモルタル壁に、かわいた蝋のかたまりのようなものがこびりついていたので、何かと思っていたら、あれはカマキリの卵だと、どこかで調べたらしい子どもが得意げに言った。親指の先ほどの、こげ茶の殻のような形状のものは卵鞘と呼ばれ、中にたくさんの卵が入っているらしい。春になったら生まれるかなと、とおるたび眺めていたが、春が来て夏が来ても、卵はおし黙ったままだった。それから四度、季節はめぐった。
昨日、出がけに低めのヒール靴の、つま先の前にカマキリがいた。はっとお互い顔を見合わせるような沈黙の時間が、カマキリとわたしのあいだに流れた。成虫で、枯れ枝のような褐色が初冬の日差しに映えた。大きくまたいでも、カマキリは沈黙の体勢のまま静止していた。だれにも踏まれないでよ、と背中で思った。列車に乗ってから、あの卵鞘のことを思い出した。
卵鞘は孵らなかった。カマキリの卵鞘には、二百から三百の卵が入っているというから、黒光りする物体を見ながら、生まれたらどうしようと考えていたが、杞憂だった。
その卵鞘がまだ壁にはりついている。邪魔になるわけでもなく、はがすのもこわい気がして、そのままになっている。いったい内部はどうなっているのかと想像することも、いささかおそろしいのでしない。ただ、春になったら、と身構えていた子どもと自分の高揚だけが、四年のあいだ宙ぶらりんになっている。四年のうちに、蔓延した未知のウイルスによって世界は激変し、子どもは小学校へ入学し、わたしは勤務先の書店を退職した。
〈あれがlifeなんだ〉の「life」とはなんだろう。生活、人生、などというよりはもっと根源的な命、と呼ぶのがいちばん近いのかもしれないが、「命」の表記ではこの詩の魅力は半減する。lifeという単語の軽やかさと、無機質な翻訳の作業が、詩人の作風としてはめずらしく口語散文的な、この詩には必要なはずだ。
故郷である香川県で、高校の英語教師をしながら詩作をつづけた詩人が、「孤独な泳ぎ手」を題名とした第三詩集を刊行したのは、教師を退職してから十三年後の一九八三年、詩人が六十三歳になる年のことだ。その前の第二詩集において、「孤独な泳ぎ手」とほぼ同じタイトルの詩が収録されていることや、「孤独な泳ぎ手」に付属するように「疲れた泳ぎ手」の詩が並んでいることは、手元の現代詩文庫を読み返して気がついた。
「荒地」の拠点から離れた地方でひとり、海とともに詩と対峙しつづけた詩人の言葉のなかに、さまざまな形の、うねるような「life」を見る。詩人にとっての海や「life」に、人はその生においてひとしく、出会うことができるのだろうか。出会えない「life」のために詩があるのか。
目次
