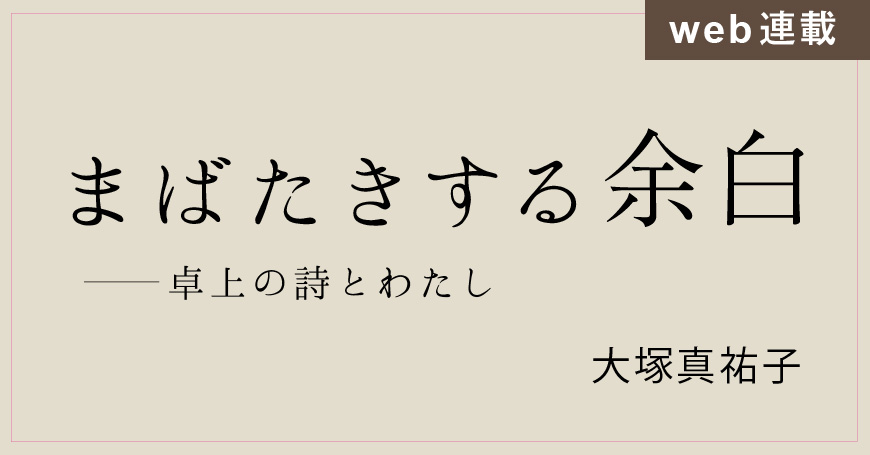
どのくらい前?
ほんのひと悲しみくらい前さ
a grief ago
と
ある詩人の言い方をまねてひとりごとをいってる
朝
やっぱり生は
死のやまいなんだよ
つまり
死は健全であって
それが病気になると生になるんだ
世界は
死に抱かれてるよ
あの世について未開人はたいてい暗いイメージを抱いてるけど
ほんとにそこはそうなのか
あの世なんてありはしないし
仮にあったとしても
こちらからは見えはしない
朝
完全に健康体である死を考えて
やまいである生を
薄い目でながめながら
だれにともなくきいてみる
きみ、いつから生きてるの?
どのくらい前?
(一九八八年/北村太郎『港の人』(思潮社)より「19」)
その日がたまたま割りあてられた休みであると、誰にも告げなかった。いつもと同じ列車に乗り、いつもとは別の駅で降りた。曇天の横断歩道を渡りながら、映画館に行こうと思った。喫茶室で遅めの朝食をとり、上映中の映画を調べ、商業施設の上階にある映画館を選んだ。喫茶室には男女二組の先客がいて、どちらも女のほうがしゃべった。
はじめて乗る列車で窓際に立つと、自分の周りを光の点が、虫のようにひらめいていた。手にした携帯電話のどこかが陽光を集め、それをまた放つのだった。駅名を確認しながら、これから降りる駅にかつて、同僚が暮らしていたことを思い出した。住まいを尋ねると駅の名を答え、けれどそこからは通いにくいから、別の路線を使うのだと彼女は言った。
駅に降り立つと大きな橋があり、川があった。広い川岸には数個のテントが見え、喧騒をくぐり映画館へ向かった。映画は妻を亡くす男を中心に、いくつかの喪失が描かれる長編だった。よかった。子どもが生まれてからめっきり遠ざかっていたが、自分の精神にはまだ、映画という表現に呼応できる場所が残っていると感じ、ほっとした。
外に出ると山並の濃い影を、隠れたばかりの太陽が火のように縁どり、その上を橙の満月が、滴りそうな近さで浮かんでいた。橋上では多くの人が、スマートフォンを空にかざし、足下にはなぜか未使用の乳児用おむつが落ちていたが、誰も気にとめなかった。そのまま改札を抜け、いつものとおり帰宅した。
川の風景とともに育ったはずの同僚は、ある朝、目覚めないまま亡くなったとのちに聞いたが、人づてに聞いた死より、またいつか、と別れた更衣室の世界線があまりに鮮やかで、彼女はいまもどこかでがんばっているのだろう、と自然と考えている。
三十三の詩篇から成る「港の人」は、大病を得た一九八七年から発表され、翌年に詩集として刊行されている。「19」は死の側から生を見すえ、生が〈やまい〉なのだとする逆説的な一節が印象にのこるが、このフレーズはすでに一九八二年に発表された「墓地の門」という詩の、最後の連に含まれている。
〈詩はことばの病、とつぶやきながら/傘をさして銭湯へ/気になって/門に振りむく/生は死の病かな?/なまめかしいだけの木立ちがある〉(「墓地の門」より)
クエスチョンに対し、やっぱりそうなんだよ、と答えているようだ。肉体に現実の死がせまったときから、詩人が詩作の向こうでつねにまさぐってきた「死」の意味やイメージと、答え合わせをしていたのかもしれない。
詩とは「直撃力」である、とかつて述べた詩人と、詩の言葉をつうじて見つめあうとき、ふいにこの肉体を邪魔だと感じる。死を詩で生きることと、詩で死を死ぬことはたしかにまったく同義なのだ。
大塚真祐子
書店勤務。『本の雑誌』の「新刊めったくたガイド」欄、日本文学の紹介を2020年12月まで2年半担当。また。朝日出版社webマガジン「あさひてらす」にて、エッセイ「何を読んでも何かを思い出す」連載中。
目次
