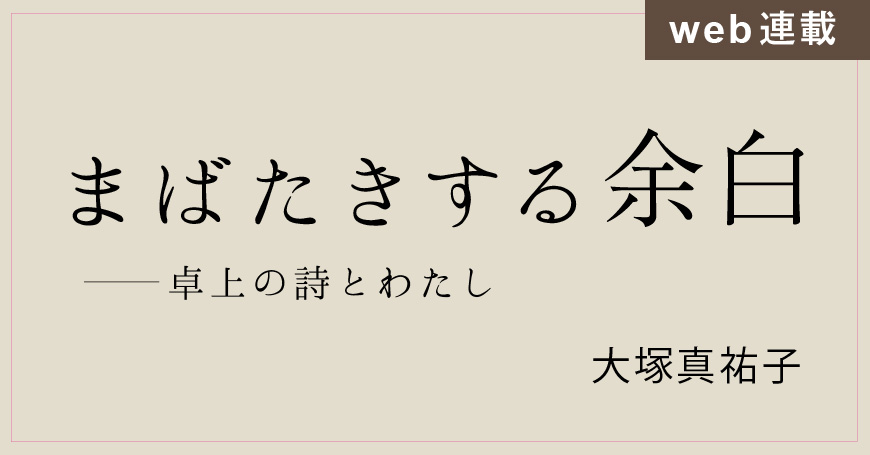
夏の中心
北村太郎
幾十もの季節が
すぎました
わたしを濾すように
「愛」といってみます
命令や
断言を避けて
何が残ったでしょうか
せいぜいおりです
「愛する」といってみます
骨の林から
風が
吹いてきます
幼年のころ
わたしは小川で
蝦をつかんだのでした
でもすぐに
跳ねて
わたしの指から消えました
小さなしぶきと
かすかな波紋を
口をあけて
見つめていました
それが
わたしの夏の中心だったのです
「愛」
「愛する」
叫ぼうとするのです
叫びが
命令であるかのように
影が
すうっと地を払い
これから
幾つの季節が
くるのでしょう
(一九七六年/『おわりの雪』(思潮社)収録)
編注:上記「夏の中心」の引用のうち、2段落目最終行の「おり」には、原典では傍点が付きます。
古い団地の小さな浴室から、いつの間にか夏の夕方がはじまっている。
くっきりと濃い影を連れて、牧歌的なクリーム色の四角いタイルを、一枚一枚ゆっくりとうらがえしている。磨り硝子の窓は、向かいの4号棟のベランダにはためく、とりどりの洗濯物を曖昧に希釈し、ハレーションを起こしている。それらがあまりに眩しいので、明かりを消し忘れたかと折戸をひらいたとき、夕方がわっと浴室の外へと溢れだし、ひび割れた部屋のすみずみまでいっせいに満ちた。平時なら子どもを学童に迎えに行く時間で、部屋にはだれもいないはずだった。夏の夕方が、この潤んだ匂いのこもる、ささやかな空間からはじまることなど知らなかった。
浴室にこもるのは、生活よりもっと生々しい、生物の生きている匂いだ。この浴室でわたしは妻をやり母をやった。ぬるま湯のなかで泣きわめく、乳児のやわらかな頭をささえるのが自分の片手のみであることを、くりかえしおそろしいと思った。
ときおり子どもが寝入ってから帰宅する夜に、わたしは浴室でわたしを脱ぐ。妻を脱ぎ、母を脱ぎ、会社員というおぼつかない体面を脱げば、そこにあるのは欲にまみれ、だらしのない、弛んだ輪郭の肉体のみだ。
北村太郎の詩や散文を読むとき、わたしにはいつも後ろめたさがある。それは、自分が本当には、この詩人のことを何ひとつわかっていないのではないか、という怯えにも似た気持ちである。
「夏の中心」を読み、理性と感情のあいだで均衡をとろうとする、その精神の揺れるさまを見たように思った。すでに過ぎた〈幾十もの季節〉をふりかえることからはじまり、これからもくる〈幾つの季節〉に思いをはせることで閉じるこの作品は、向日的な題名とは裏腹に、何かの不穏な予感、あるいは悲壮な覚悟に満ちている。その源に何があるのか、自伝『センチメンタルジャーニー ある詩人の生涯』や、ねじめ正一の『荒地の恋』、橋口幸子による『珈琲とエクレアと詩人・スケッチ北村太郎』をはじめとする一連の随筆を読んだいまなら、わかるように思う。「夏の中心」はちょうど、二十年以上勤めた朝日新聞社を退社し、田村隆一の妻和子との恋愛があきらかになった年に書かれている。
勤め人として、また夫として父として、模範的にふるまう本名の松村文雄と、友人の妻と恋愛をし会社を辞め、家を出てからあらためて多数の詩作を生んだ詩人の北村太郎と、一見相反する二面性にどうしようもなく響きあう自分がいる。夏の夕方はすでにありふれた表情をして、窓枠の地平にまぎれようとしている。浴槽に湯をはりながら、そのしぶきと波紋のなかに、詩人の眼差しを何度も見た。わたしはこれからどうすれば、あなたを生きられるだろうと考えている。
大塚真祐子
書店勤務。『本の雑誌』の「新刊めったくたガイド」欄、日本文学の紹介を2020年12月まで2年半担当。また。朝日出版社webマガジン「あさひてらす」にて、エッセイ「何を読んでも何かを思い出す」連載中。
港の人が信頼する書店員のひとり、大塚真祐子さんには、これまで冊子「港のひと」などに執筆をお願いしてきましたが、このたびこの場所で、詩について定期的に書いていただくことになりました。次回は10月に更新の予定です。
目次
