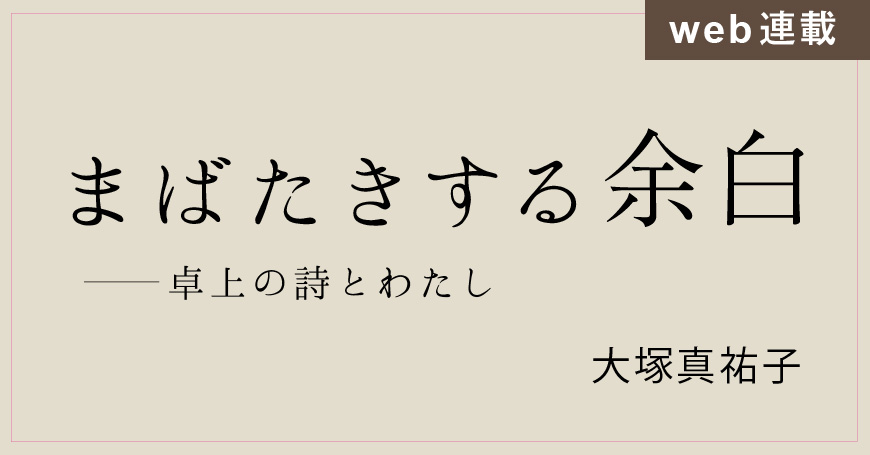
帰途
田村隆一
言葉なんかおぼえるんじゃなかった
言葉のない世界
意味が意味にならない世界に生きてたら
どんなによかったか
あなたが美しい言葉に復讐されても
そいつは ぼくとは無関係だ
きみが静かな意味に血を流したところで
そいつも無関係だ
あなたのやさしい眼のなかにある涙
きみの沈黙の舌からおちてくる痛苦
ぼくたちの世界にもし言葉がなかったら
ぼくはただそれを眺めて立ち去るだろう
あなたの涙に 果実の核ほどの意味があるか
きみの一滴の血に この世界の夕暮れの
ふるえるような夕焼けのひびきがあるか
言葉なんかおぼえるんじゃなかった
日本語とほんのすこしの外国語をおぼえたおかげで
ぼくはあなたの涙のなかに立ちどまる
ぼくはきみの血のなかにたったひとりで帰ってくる
(一九六二年/『言葉のない世界』(昭森社)所収)
神保町という街を想起するとき、なぜかそれはいつも正午にちかく、雑然と積まれた背表紙に陽光が垂直に射して、ハレーションを起こしている。近くの会社に勤める人びとが靖国通りをいっせいに歩きだすかたわらで、店先の古書を品定めする人たちの視線が、無言のうちに交差する。
神保町とは自分にとって長らく、古書の街でもカレーの街でもなく、祖母の営む書店の仕入先のある街であった。小さな卸業社が町の一角に集まる「神田村」と呼ばれる場所へ祖母は毎日のように通い、風呂敷いっぱいの本を担いで帰ってきた。たまの週末は父の車で神保町へと向かい、祖母が問屋へ残した荷物を積みこんでから祖母に会いに行くこともあった。入社した書店でたまたま神保町の店舗に配属されたことを伝えると、祖母は仲間ができたというように、本屋の仕事の大変さをとうとうと語りはじめた。まったく楽な商売じゃないよと繰りかえしながら、結局は亡くなる二年前まで七十年近く、祖母は本屋を営んでいた。意図したわけではないが、孫の自分は祖母が通うことのなくなった神保町に十年以上勤めることとなり、いつしか神保町のさまざまな表情を目にすることとなった。
週末は近くの古書店でガレージセールがひらかれるので昼食を早めにきりあげ、ワゴンに群がる男性たちの横へ会社の制服姿でまぎれこんだ。購入する本は単なる自分の好みのこともあれば、古本のイベントなどで値付けをし、個人的に販売することもあった。ひんやりとうす暗いガレージで書棚に目をこらしながら、この小さな世界のことを言葉で表してみたいという欲求について考えた。身のまわりに生まれては消える無数の小さな渦のはざまで、たえず揺らめく肉体を感受しながら、自分がここにいることをだれかに伝えたいと思うとき、それが言葉に正しく置きかえられたときだけ、肉体はしかるべき場所へと降り立ち、ようやく世界の一端に触れられたような感覚があった。どうすればもっと言葉で伝えることができるだろう、と考えながら伸ばした手の先に数冊の現代詩文庫があり、『田村隆一詩集』もそこにあった。所有していない現代詩文庫を見つけたら、必ず買うと決めていた。以前に持っていたものは別れた恋人に貸したまま戻ってこなかった。
そのときは気づかなかったが、『田村隆一詩集』にはあちこちに書き込みがあった。消しゴムがかけられていたが、筆圧から文章が読みとれる箇所がいくつもあった。前半に集中してかなりの書き込みが認められたが、印象的だったのが「帰途」のページに書かれていたこの文章だった。
〈二、三日って考えて、詩なんかなくたって、愛し合っていけばいい〉
これが「帰途」への返答であるとしたら、詩人はなんと言うだろう。わたしは詩の言葉と書き込みの筆圧の間に降り立って、ときどきそれぞれの葉ずれをじっと眺めている。
大塚真祐子
書店勤務。2022年4月より、毎日新聞文芸時評欄にて書評を担当。朝日出版社WEBマガジン「あさひてらす」にて、エッセイ「何を読んでも何かを思い出す」連載中。
目次
