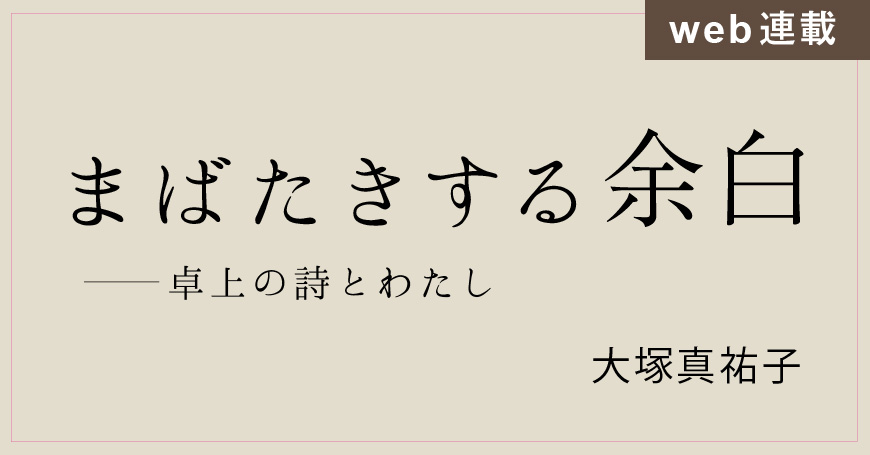
彗星的な愛人
永瀬清子
象徴の相貌をもてる我が愛人よ
貴方は呆けた野道の花のやうに飛びやすい。
貴方はどこか太陽よりももつと遠い天体からの光の中に棲息してゐる。
私は陽のさす半球に坐つてゐるから
いつもたゞ空しく想念のうちにのみ貴方を追ふ。
けれどもかつて私は貴方をまざまざとみた。
私はこの世の果に於て貴方を感じた。
明るみと闇との両半球の
不思議な崖ぶちで貴方をみた。
私が貴方に最後のさやうならの手を揚げて以来
もう何年たつのだらう。
今は私は時間の遠さをすつかり忘れてしまつた。
何十年何百年、あゝもつともつと長い間私は貴方を見失つてゐる。
その長い、あまりにも目のくらむ遠い時間を
私はただ自分の失つたものへと痛み暮した。
去りたる恋人よ
私はこれから先、何年生きるのか。
否何十年何百年生きるのか
私の身体には苔の花が咲き
私の瞼毛は日かげの龍の鬚のやうにのび、頬へと垂れ
それでも私はたゞ一人坐つて貴方へと悲しむ。
我が恋人よ、何処にあつてももはや私に現れようとしないのか
私たちがはじめて唇を合せようとし
そして何か恐れてためらひ止まつた時の
あの密度濃い空気は、今どこの宙間を流れてゐるのだ。
あゝ貴方自身も暁の光の中へでも化合したのか。
でなければほの白いその光の中で
不意に私に滞在の涙の湧くのは何故だらう。
もしくは暁が つめたい微風をともなひ
静かに夜を発つ時
多分知らずに私は貴方から一歩遠ざかつてゆかうとしてゐるのだらう、その涙は、
一夜の盲目な彷徨を終つて――。
さうだ、かつて貴方が私にあらはれた時、
そんな陽のものとも思へぬ光に乗つて来た。
貴方はあけ方の野末の雑草の中を私と迷ひ
そしていつか消えて行つた。
その時貴方は母の面影をもつてゐた。
おゝ草の微毛のやうにとびやすいものよ
複数の相貌をもてるものよ。
私は昼間あかるい中に坐つて
真空の中でのやうに物忘れしてゐる。
涙はかわき 自身は軽いばかりだ。
たゞふとひどく暗い展覧会の片隅などで
おゝ、こゝに彼のパレツトから来た色がある! と
一瞬に何百年の谷をとび降りることがある
否々けれども私はいつもちがつてゐるのだ
私は粗忽の重い罰で
憂鬱に平癒の細道を再び這ひ上らねばならぬ
又ひどくかびくさい古道具屋で
ふと、あゝあすこにあるのは幼い私たちが一所に造つた玩具の軍艦だ! と思ふのだ。
でも駄目々々、やはりそれはちがつてゐる。
私は決してこの陽に傾斜する半球で彼をみる事は出来ない。
おゝ飛びやすきものよ
彗星めくものよ
太陽熱をともなはぬ愛人よ
私らは永久に反対の半球に住み
たゞ悲しみの本能ばかり残つて
いつもたゞ空しく想念のうちにのみ貴方を追ふ。
(一九三〇年/『グレンデルの母親』(歌人房)収録)
編注:第2連の「まざまざ」は、原典では踊り字が使われています。
週末は団地の自治会による恒例の餅つきがあり、朝から三角巾とエプロンを持参して、持ち回りの手伝いをした。集会所の入口にはすでに蒸したもち米のかおりがただよい、たくさんの住民が集まっていた。おはようございます、と声をかけて中へ入ると、大きな銀のボウルやバット、あんこが入った番重などが、長机の上に用意されている。わたされた手書きの名札を胸につけると、てきぱきと指示を出し合う年上の女性たちにはさまれ、ひたすら自分の役割をさがした。
子どもが生まれてから古い団地に住みはじめたが、日中は仕事で不在にしており、すすんで行事に参加するような社交性もなく、周りは見知らぬ女性ばかりである。が、作業をするうちに目の前の手仕事を介して、おのずとやりとりや対話が生じはじめた。あんこが固いわとつぶやく人、餅切り機の前で要領よくバットを交換する人、次いきまーすというかけ声、はーいという返事、雑多なにぎわいのなかで、なにげない所作にその人の生活や人となりが、ふいにありありとあらわれる。役割を見つけながら半日、餅と格闘した。どうぞ持って帰ってと、餅を3パック持たされた。調理用のゴム手袋を外すと、右の薬指にささくれができていた。
十七歳で『上田敏詩集』に出会い、詩にひき寄せられた永瀬清子は、結婚出産を経て、戦後に郷里の岡山県赤磐へ戻り、生まれてはじめての農業に従事しながら詩を書きつづけた。戦時中に書いた作品を集めた『大いなる樹木』、戦時からの解放を率直にうたう『美しい国』、農村の風景がはしばしにのぞく『焔について』などを順に読むと、詩人の言葉がその日そのときの生活に、深く根ざした場所から生まれていることがわかる。そして詩作と日々の労働にひとしく対峙した詩人が、その内側に秘めたある激しさのようなものも、詩編の数々から見てとることができる。
第一詩集に収められた「彗星的な愛人」からは、しなやかで切実な呼びかけのうちに、ゆるぎない眼差しの逞しさを見た。連なりからあふれる苛烈な情愛のうちに、無限に放射する絶対的な孤独を見た。岩波文庫『永瀬清子詩集』に収録された谷川俊太郎との対談によって、この詩の背景に母方の二人の従兄への思慕があったことを、はじめて知った。
薬指のささくれを指でつまんだとき、思い出した人があった。ひっぱるとささくれは思いのほか深くめくれ、血がにじんだ。あの人もそうだった。傷やできものを平気でえぐって、こうすれば早く治ると言うのだった。
番重のあんこを割箸で掬う自分と、赤らんだささくれを眺める自分が、詩人のなぞる真空の部屋で向かいあう。あの人に似てしまう所作のことを、この部屋は気づいている。わたしがわたしの想念の軌道を追うことを、これら詩の一連のみがわたしに許してくれる。
大塚真祐子
文筆家・元書店員。
2022年より毎日新聞文芸時評欄担当、朝日出版社WEBマガジン「あさひてらす」にて「何を読んでも何かを思い出す」連載中。
執筆のご依頼はこちら→komayukobooks@gmail.com
目次
