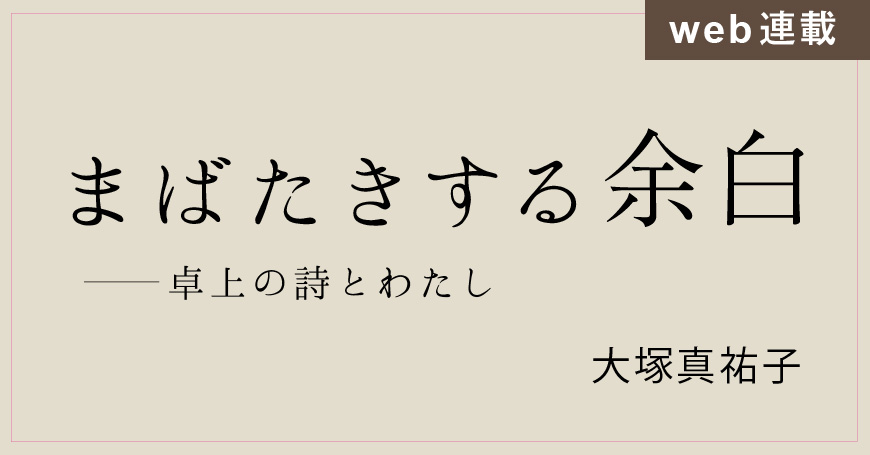
北鎌倉
北村太郎
宵のくちから眠たがるのは、夕惑い
コーヒーを飲み終わる朝から、もう眠いのでは
朝惑い、じゃないか
だから、せめて物でも見ようと
岸辺へ、ふらふら歩いてゆき
小高い岩によじ登って、海をながめる
こんな頭では、目をこらしても
定かに、かたちなぞ見られるものかと
それでも、広い水のおもてに顔を向けているうちに
(おや、またあの小波の集まりだよ)
あらしの先なのか後なのか、それとも
ちがうわけからなのか、知らないが
海には低い青の穂波が、おびただしく
はるかな沖まで立っていて、お互いに
消しあい、起こしあっている
それなのに、音はほとんど聞こえない
目に騒がしく、耳に静かな
この海のすがた、いつも心が慰められる
すこし頭が、すっきりし
昼から、よこはまへ遊びに行く
北鎌倉で、窓からプラットフォームへ目を移すと
かばんを持った子どもたち、ののしりあっていて
たまたま、ひとりの手が
木の柱に、縦に打ちつけてある
きたかまくら、と白く記した金物の板に
すっ、と伸び
ごく短いあいだ、「か」だけが隠れる
あくびをしながら、声に出して読んでいる
(一九九二年/『すてきな人生』(思潮社)収録)
大船を過ぎたころ、すでに雨は大粒の雪に変わり、車窓をゆっくりとなぞるようにたえまなく落ちていた。北鎌倉の駅に降り立ったのは、わたしたちともうひと組の男女、数名の住民と思われる人びとのみだった。冷気が足裏から内臓へ沁みこむように広がって、ひとまず目当ての寺へ向かうことにした。
休日を合わせ、鎌倉でも行こうかと横浜の地下街で待ち合わせたときは、まだ雨だった。三月の終わりに雪が降ることを、わたしたちは想定していなかった。寺へ向かう歩道は車道と区切られておらず、わたしは雪の向こうに彼の背を追った。水分を多く含んだ雪は、アスファルトにとどまることなく溶けた。
寺では、境内の墓苑に眠る作家らの墓参りをするつもりだった。茅葺きの小さな山門をくぐり参道をすすむと、思いのほか奥まった墓苑がある。樹木にかこまれ、晴れていれば風とおしもよさそうだが、なにしろ雪なので、苔むした石段をすべらないよう、足もとばかり見ていた。木々の根元は白々として、雪が積もりはじめていることがわかった。
参道を引きかえし、ひとまず屋根のある建物に入ると、袈裟をまとった木造の菩薩像が祀られ、寺の案内が壁に掲示されていた。そこではじめてこの寺が、女人救済の縁切り寺であることを知った。すでに靴のなかへ雪水が入りはじめており、掲示を熱心に読むふりをして、上半身だけわずかに暖をとった。谷戸の地形に広がる境内に、四季の花が咲くこともそこで知ったが、眺める余裕はなく、狂ったように白木蓮に舞う雪と、わずかに残る蠟梅の小さな明るさを覚えている。積もりはじめた車道を、わたしたちはふたたび駅へと戻り、冷えた身体を温め合いながら車内でひととき、深くふかく眠った。
北村太郎の詩に、頻繁に書かれるモチーフのひとつに海がある。死の年に書かれた「北鎌倉」にも、波立つ海とそれを見つめる詩人の姿が切り取られるが、三十歳のときに詩人は、はじめの妻子を海の事故で亡くしている。その記憶をこじ開けるように、海はたびたび彼の詩に現れた。
「あなた、わたしを生きなかったわね」という声が複数の詩に登場することについて、自伝では明確に〈死んだ彼女〉、つまり亡き妻の言葉として語られているが、妻子の死を詩人が詩で生きていたことは間違いなく、その表出のひとつの形として、海があったと思う。
このことをどう名づけたらいいのか。弔いとか悼みとかましてや愛だとか、既存の単語の軽薄さには到底おさまらず、詩人の生と詩と死が一体になって言葉の海を泳ぎもがいていた、と表すことしかわたしにはできない。北村太郎という人にどうしようもなく惹きつけられるのは、言葉のなかに肉体を投げこみ、そのどちらもを激しく、誠実に生きたからで、わたしはたえずその姿に問われているのだ。あなたはわたしを生きないの?と。
大塚真祐子
書店勤務。『本の雑誌』の「新刊めったくたガイド」欄、日本文学の紹介を2020年12月まで2年半担当。また。朝日出版社webマガジン「あさひてらす」にて、エッセイ「何を読んでも何かを思い出す」連載中。
目次
